池袋の弁護士・田村優介です!
先日、日本経済新聞に、「社員の懲戒、社内公表は名誉毀損か 再発防止に悩む企業」と題する記事が掲載されました。
「社員の懲戒、社内公表は名誉毀損か 再発防止に悩む企業」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG016II0R01C24A1000000/
本記事では、懲戒処分を社内に公表する行為が名誉毀損に該当する可能性や、その判断基準を弁護士がわかりやすく解説します。
プライバシーと組織の秩序維持を両立させるために、どこまで情報を共有し、どのように公表するべきかを明確にし、従業員との紛争回避にもつなげるポイントを学ぶことができます。
最終的に、不必要に広く情報を拡散すれば名誉毀損が成立するおそれもありますが、正当な目的で必要な範囲にとどめれば問題ないことがわかります。また、具体的な設例を通じて、どのような場合に公共性や真実性が認められるかのポイントを学ぶことで、懲戒処分の発表によるリスクを最小限に抑える方法を理解できるでしょう。こうした知識を身につけることにより、企業が適切な情報開示と法的リスクの回避を両立させる術を学べます。
1. 懲戒処分の社内公表は名誉毀損になる可能性がある
懲戒処分の事実を社内で公表する行為は、従業員の名誉を大きく損なう可能性があるため、名誉毀損として法的責任を問われるリスクを伴います。一方で、企業としては社内規律を維持し、再発防止を図るために一定の情報共有が必要となる場合もあります。この両立をどう図るかが経営上の重要な課題であり、就業規則やコンプライアンス体制の整備を十分に行うことが求められます。
社内で懲戒処分を発表する際には、対象者のプライバシーや名誉が不当に侵害されないように配慮することが重要です。処分を公表された従業員が後に名誉毀損や損害賠償を主張することもあり得るため、企業は自社の就業規則や懲戒規定を踏まえたうえで、弁護士等の専門家に相談しながら公表範囲や内容を慎重に検討する必要があります。
1.1 名誉毀損の成立要件
名誉毀損は、刑法上だけでなく民法上も成立が認められる場合があります。一般的に、以下の要件を満たすと名誉毀損が成立すると考えられています。
| 要件 | 具体例 |
|---|---|
| 1. 公表行為 | 従業員向けの全社メールで懲戒処分の詳細を一斉送信する |
| 2. 事実の摘示 | 「○○氏が就業規則違反を行ったため~」など、個人を特定できる詳細を示す |
| 3. 名誉を毀損する事実 | 企業の社会的評価を下げ、対象者の評判を低下させるような事実を広く伝える |
| 4. 違法性 | 公共性や真実性、公益目的がない場合や表現方法が不当な場合 |
懲戒処分を社内で公表すること自体は、社内秩序を保つための正当な行為とみなされ得る場合もあります。しかし、名誉毀損が成立しうる行為に該当しないよう十分に配慮しつつ情報を共有することが欠かせません。
1.2 懲戒処分の公表で名誉毀損が問われるケース
懲戒処分を公表する行為が名誉毀損と判断されるかどうかは、情報の開示範囲や内容、目的などによって左右されます。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。
1. 不必要に細かい情報の開示
社内での告知に際し、処分の理由を詳細に暴露しすぎたり、必要以上に個人情報を公開したりすると、過度な名誉やプライバシーの侵害にあたる可能性があります。
2. 公表範囲の不適切な拡大
処分対象者の部署だけでなく、業務に無関係な全社員や取引先企業などにまで通知が行われると、逸脱した名誉毀損に該当する危険性が高まります。
3. 虚偽や誇張が含まれる場合
懲戒処分の原因となった事実を誤って伝えたり、実際よりも過度に悪質な表現を使ったりすると、対象者から誤った事実を流布されたとされ、名誉毀損の訴えを起こされるリスクがあります。
1.3 懲戒処分の公表が名誉毀損にならないケース
一方で、企業活動上やむを得ない範囲にとどまり、情報を必要最低限に絞った正当な懲戒処分の公表であれば、名誉毀損として違法性が否定される場合もあります。以下のようなケースがこれに該当します。
1. 公益性・公共性をともなう公表
社内の安全や信頼関係を維持するために必要な範囲で情報を共有することが求められるケースでは、処分公表の意義が社会的に認められやすくなります。
2. 真実性のある事実を根拠とする
処分内容とその根拠が客観的に正しい事実に基づくもので、公表範囲が適切であれば、名誉毀損として違法性が問われにくくなります。
3. 目的が正当で表現手段も必要最小限
対象者をいたずらに貶めることを目的とせず、社内の秩序維持や再発防止を念頭に置いた丁寧な公表方法であれば、名誉毀損に該当しづらいと考えられます。
2. 懲戒処分の種類と社内公表の範囲
懲戒処分は、企業が社内秩序を維持し、コンプライアンスを徹底するうえで欠かせない手段です。しかし、対象従業員には名誉やプライバシーがあり、名誉毀損などの法的リスクにも配慮しなくてはなりません。ここでは、代表的な懲戒処分の種類と、社内で公表する際の範囲や注意点について解説します。
2.1 懲戒処分の種類
企業は労働契約法や就業規則などに基づいて、従業員の違反行為に応じた複数の懲戒処分を行うことができます。どの処分を科すかは、違反行為の重大性だけでなく、企業の秩序維持や再発防止策も考慮して慎重に判断されます。以下の表では、代表的な懲戒処分の概要と、社内に公表する際の留意点をまとめています。
| 処分の種類 | 概要 | 社内公表時の留意点 |
|---|---|---|
| 譴責 | 違反行為に対して、文書もしくは口頭で厳重な注意を行う処分。 | 公表の範囲を必要最小限にとどめ、名誉毀損リスクを回避する。 |
| 減給 | 一定期間、給与の一部を減額する処分。労働条件が変動するため、就業規則等に沿った手続きが必要。 | 公表する際は対象者の個人情報を厳重に管理し、社内不安を煽らない配慮が求められる。 |
| 出勤停止 | 就業を一定期間停止させる処分。給与も減額となる場合が一般的。 | 処分日数や根拠を明確化しつつ、公表しすぎによる名誉毀損を防ぐための情報限定が必要。 |
| 降格 | 役職・職位を引き下げる処分。組織へのダメージが大きいあらゆる不正行為に適用される場合がある。 | 降格の理由を細部まで広く周知しないよう注意し、必要な最低限の情報を開示する。 |
| 諭旨解雇 | 退職届を提出するよう促し、事実上の解雇となる処分。違反行為が重大であるケースで適用されることが多い。 | 公表範囲を誤ると従業員の名誉を大きく損なう恐れがあり、慎重な判断が求められる。 |
| 懲戒解雇 | 解雇の中でも最も重い処分。横領や背信行為など、企業の信頼を揺るがす重大な違反行為が原因となる。 | 社会的信用の失墜を伴いやすく、解雇理由の説明には名誉毀損のリスクを常に意識する必要がある。 |
2.1.1 譴責
譴責は軽微な違反行為に対する処分であり、本人に対して反省を促すことが主な目的です。社内公表においては、余計な情報を伝えすぎないようにすることで、本人の名誉を過度に傷つけないよう配慮が求められます。
2.1.2 減給
減給処分では対象者の賃金が一時的にカットされるため、従業員間での不安や不満が高まりやすい側面があります。公表する場合は金額まで詳細を伝える必要があるかを慎重に検討することが重要です。
2.1.3 出勤停止
出勤停止は業務からの隔離期間を設けて再教育や反省を求める意図を持ちます。企業としては、どの程度の期間か、何をもって復職とするかを明確に示すと同時に、その詳細を社内で共有する範囲を限定することが大切です。
2.1.4 降格
降格は役職や職位を下げるもので、処分された従業員にとっては社会的な信用の低下につながる恐れもあります。公表の際は周囲に動揺を与えないよう、企業としての適正な手続きを踏んでいることを簡潔に伝える姿勢が大切です。
2.1.5 諭旨解雇
諭旨解雇は、会社側が退職届の提出を求める形式の重い懲戒処分です。信頼関係が大きく損なわれた場合に選択されますが、公表内容によって本人の名誉を極端に低下させる危険もあるため、慎重さが欠かせません。
2.1.6 懲戒解雇
懲戒解雇は最終手段としての位置づけであり、極めて重大な労働契約違反があった場合に適用されます。法的リスクが高いため、社内公表では必要な事実を正確に伝えつつ、プライバシー保護にも充分配慮する姿勢が要求されます。
2.2 社内公表の範囲
懲戒処分を社内で周知する目的は、他の従業員に対する注意喚起や予防効果、企業秩序の回復などが挙げられます。ただし、あまりに広く公表すると名誉毀損のリスクが高まるため、以下のような要素を考慮して決定することが肝要です。
2.2.1 対象者
公表対象は直接的に業務上関係する上司や同僚、当該部署などに限定することが一般的です。処分を行った部署以外まで周知を拡大する際には、処分の必要性と公表によるプライバシー侵害のバランスを十分検討しなければなりません。
2.2.2 公表方法
公表の方法は社内メール、掲示板、会議での報告など、企業の慣行や就業規則によってさまざまです。重要なのは、その方法が合理的に限定されたものであるかどうかです。不要に広範囲に情報を流してしまうと、名誉毀損のリスクが高まる点に注意が必要です。
2.2.3 公表内容
公表すべき内容は、違反行為の概要や処分の種類、再発防止策などにとどめるのが望ましいとされています。個人の私生活に関わる情報や、企業が得た機密情報などを必要以上に暴露すると、名誉毀損リスクが増大するため注意が必要です。
3. プライバシーや名誉への配慮と社内の規律維持の両立
社内規律の維持は企業の秩序を守るうえで欠かせない一方で、従業員のプライバシーや名誉を安易に侵害しないよう十分な配慮を行うことも求められます。懲戒処分を社内で公表する際には、このバランスをどのように保つかが重要な課題となります。名誉毀損のリスクをはじめとする法的トラブルを回避しつつ、企業側としては公正な処分を行い、従業員に正しいメッセージを伝えることが不可欠です。
過度な情報開示は個人のプライバシーを脅かし、社内での人間関係を悪化させる恐れがあります。また、的外れな公表方法が原因で名誉毀損による訴訟リスクが高まる場合もあるため、慎重な判断が必要です。具体的には、懲戒事由や処分内容を開示する範囲を必要最小限にとどめ、情報を知る必要がある従業員に対して適切かつ公平に伝達を行うことが理想とされます。以下では、プライバシーや名誉への配慮と社内の規律を維持するために必ず押さえておきたいポイントを解説します。
3.1 必要最低限の公表
懲戒処分の社内公表にあたっては、法的根拠や業務上の必要性を十分に検討し、公表範囲を最小限にとどめることが重要です。処分の対象従業員や関係部署への説明は不可欠ですが、全社員に一律で詳細を知らせる必要があるかどうかは慎重に検討すべきです。周知内容が広範に及びすぎると、プライバシー侵害や名誉の毀損に発展するリスクが高まります。
次の点を踏まえて、必要最低限の公表を実践することが望ましいでしょう。
| 項目 | 具体的な配慮方法 |
|---|---|
| 情報の範囲 | 処分を公表する際は「懲戒処分を受けた事実」と「再発防止のための要点」のみにとどめるなど、個人の詳細情報を必要以上に開示しない |
| 公表先 | 関わりのある部署や上長など、周知の必要がある対象者だけに絞る |
| 公表時期 | 社内研修や定期ミーティングなど、適切なタイミングを選び、多くの従業員の前で一斉に発表しない |
3.2 公正な手続き
社内規律を維持するための懲戒処分であっても、公正な手続きに基づき適切な判断が行われているかがチェックされないと、トラブルになる可能性が高くなります。公正な手続きのポイントとしては、調査過程の透明性や被処分者への十分な弁明機会の付与などが挙げられます。
また、公正な手続きを踏むことで、処分理由に納得感を持たせられるだけでなく、社内公表の際にも「適切なプロセスを経て下された判断」という認識を従業員に共有できます。このような認識が周知されれば、会社側による不当な名誉毀損やパワハラといった誤解を招くリスクが低減すると考えられます。
3.3 適切な表現
懲戒処分を公表する際の表現には十分な注意が必要です。過度にネガティブな表現や個人の人格を否定するような言葉を用いると、たとえ事実を伝えているだけでも名誉毀損とみなされる恐れがあります。事実関係を正確に伝えると同時に、ビジネス文書として不適切な表現が含まれないよう念入りに確認します。
また、公表文書の文量やトーンにも配慮し、読んだ人が混乱しない程度の情報を簡潔にまとめることが大切です。とくに、名指しや誇張などの修飾語が多いと、不必要な誤解や社内外でのトラブルの原因になりかねません。
3.4 懲戒処分に関する社内規定の整備
最後に、懲戒処分を適切に運用し公表するための社内規定を明文化しておくことが欠かせません。あらかじめ公表する範囲や方法、情報開示に関する責任者を明確にしておくことで、いざというときに迷わず対応できます。さらに、名誉やプライバシーの保護方針も含めて規定を作成することで、従業員に対し「この会社は公平かつ誠実に対応してくれる」という安心感を与えられます。
社内規定は定期的に見直し、最新の法令や判例にも対応させることが望ましいでしょう。そうすることで、社会情勢の変化や業務の拡大に伴う社内体制の変化にも柔軟に対応し、プライバシー保護と社内規律の維持を両立させることができます。
4. 懲戒処分に関する社内公表の事例
懲戒処分を公表する際には、プライバシーや名誉に配慮しつつ、組織の規律維持を図ることが求められます。実際には、処分の公表範囲や内容を誤ることで名誉毀損やプライバシー侵害が問題化するケースも存在します。以下では、実際に起きやすい事例を通じて、公表時に注意すべきポイントや対策を取り上げます(実際の事例をベースにした架空の設例です)。
4.1 事例1 社内メールでの懲戒処分の公表
「懲戒処分を受けた従業員の情報が一斉送信メールで社内に周知された」ケースを見ていきます。
情報共有の必要性は理解できるものの、処分理由や個人の経歴など、過度に詳細な内容まで含まれていたため、大きな問題に発展しました。
4.1.1 経緯
元々、会社側は同様の違反行為を防止する目的で処分内容を周知しようと考え、その従業員の行動詳細や内部規定違反の具体的事項を含めたメールを全従業員宛に送信しました。すると、他の従業員から「プライバシーに配慮がない」との声が上がり、処分を受けた従業員本人から名誉毀損やプライバシー侵害を指摘されます。
4.1.2 結果
会社はすぐに再発防止策を講じ、社内メールの文面を最小限の事実に留める運用へと改めました。しかし、その後も従業員との間で感情的な対立が続き、信頼関係の修復には時間を要しました。特に、個人の情報を組織全体へ共有する際の範囲と方法は慎重に検討すべきであることが再認識されました。
| 公表方法 | 懸念点 | 対策 |
|---|---|---|
| メール一斉送信 | プライバシー漏洩・名誉毀損のリスク | 必要最低限の情報に限定し、本人の権利に配慮 |
4.2 事例2 懲戒処分を受けた従業員による反訴
次は、「懲戒処分を受けた従業員が、その公表方法に問題があるとして労働審判や訴訟に発展」した事例を取り上げます。従業員には、処分が不当であるという主張だけでなく、公表自体によって信用失墜や精神的苦痛が生じたとする反訴の可能性があります。
4.2.1 経緯
ある従業員が業務上の不正行為を行い、懲戒処分を受けました。会社側は、企業理念に反する重大な行為だと判断し、処分結果を「懲戒解雇」に加えて社内掲示板への掲載という形で公表しました。これに対し、従業員は解雇措置の取り消しと、公表によって個人の信用が著しく損なわれたとして訴えを提起しました。
4.2.2 結果
裁判では、懲戒理由や処分自体の妥当性に加え、社内掲示板への掲載範囲や記載内容も争点となりました。最終的には、掲示板に掲出した内容が必要以上に本人を悪印象づける表現だったと一部認定され、会社側が一部の謝罪と損害賠償を行うことで和解が成立しました。会社は、就業規則の見直しや公表手順の明確化を早急に進めることになりました。
| 争点 | 当事者の主張 | 影響 |
|---|---|---|
| 処分の妥当性 | 会社:重大な業務上の不正 従業員:不当な懲戒 | 就業規則の規定内容が鍵となった |
| 公表方法 | 会社:再発防止のため社内掲示板に掲示 従業員:過度な名誉毀損 | 過度な表現があったかが争点に |
4.3 事例3 公表範囲を誤ったことによる名誉毀損
最後に「懲戒処分の詳しい経緯を本来の必要範囲を超えて公表してしまい、受けた従業員が名誉毀損を訴えた」事例を見ていきます。
多くの場合、社内規律の強化を狙って行われる公表ですが、対象従業員の社会的評価を下げるリスクが高いため、慎重さが必要です。
4.3.1 経緯
ある企業が、従業員の不正行為に対して出勤停止の懲戒処分を下しました。社内ルールの徹底を理由に、人事部が社内全員に処分の詳細と処分歴を閲覧可能な状態へ設定してしまいます。すると、強いバッシングを受けた従業員が、会社の対応は社会的評価を毀損するものとして精神的苦痛の賠償を求める事態に至りました。
4.3.2 結果
会社は社内ポータルの運用を即時見直し、多くの従業員がアクセスできるページから懲戒処分の詳細を削除しました。しかし、名誉毀損を受けた従業員の訴えはそのまま続き、最終的に和解金の支払いを通じて解決されることになりました。この件をきっかけに、会社は改めて公表範囲の設定や文言選択の重要性を認識し、ガイドラインを強化しました。
5. 懲戒処分と社内公表に関するFAQ
5.1 Q. 懲戒処分を受けた従業員が退職した場合、公表する必要はあるか?
懲戒処分を受けた従業員が退職した後にその処分を社内に公表するかどうかは、企業の内部規定や社会通念の観点から判断されることが多いです。具体的には、すでに退職している従業員について社内の秩序維持という観点がどの程度必要か、名誉毀損やプライバシーへの配慮が必要かといった点を検討しなければなりません。
実際には、在職中の他の従業員への注意喚起や再発防止の目的など、一定の範囲で公表が求められるケースもあります。ただし、個人情報を過剰に取り扱うと名誉毀損を招いてしまいかねません。公表の必要性が乏しい場合や、本人が退職して不利益を与える意義が乏しい場合は、処分を公の形で知らせるよりも社内の関係部署のみが情報を共有するにとどめる選択肢もあります。
5.2 Q. 懲戒処分の内容を公表することで、他の従業員のモチベーションに悪影響が出ないか?
懲戒処分の詳細を社内公表することは、他の従業員への警告や再発防止策としての効果が期待できる一方で、職場内のモチベーション低下や不信感を招く危険性もあります。特に、あまりにも厳しい表現や過剰な情報開示が行われると、職場全体が萎縮し、業務効率やチームワークにマイナスの影響を及ぼしかねません。
そこで重要なのは、必要最低限の公表範囲を見極めることです。公表する際には、処分理由や処分内容を事実に基づいて簡潔にまとめ、懲戒解雇や減給など処分の種類および違反行為の内容を明確化しながら、他の従業員が過度に不安にならないよう配慮ある言葉選びを心がけましょう。
6. まとめ
今回解説したように、懲戒処分の公表には、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクが伴います。その一方で、社内規律の維持や遵守意識の向上を図るためにも、ある程度の情報共有は必要です。公表方法や範囲を慎重に選定し、処分の理由を正確に示すことで、従業員に対して不当な不利益が生じないよう配慮すると同時に、不正行為の再発防止にもつなげることができます。必要最小限の表現であっても、正当な理由に基づいて明確に行われれば、社内外からの理解が得られやすくなると考えられます。適切な対応を心掛けることで、企業の信頼性を高め、安心して働ける職場づくりに寄与することが期待できるでしょう。
弁護士田村優介へのお問合せはこちらから!
ブログの更新情報はTwitter(X)でお知らせしています!フォローお願いします
東京・池袋 社長の夢を叶えるコーチ弁護士・田村優介(第二東京弁護士会・城北法律事務所)
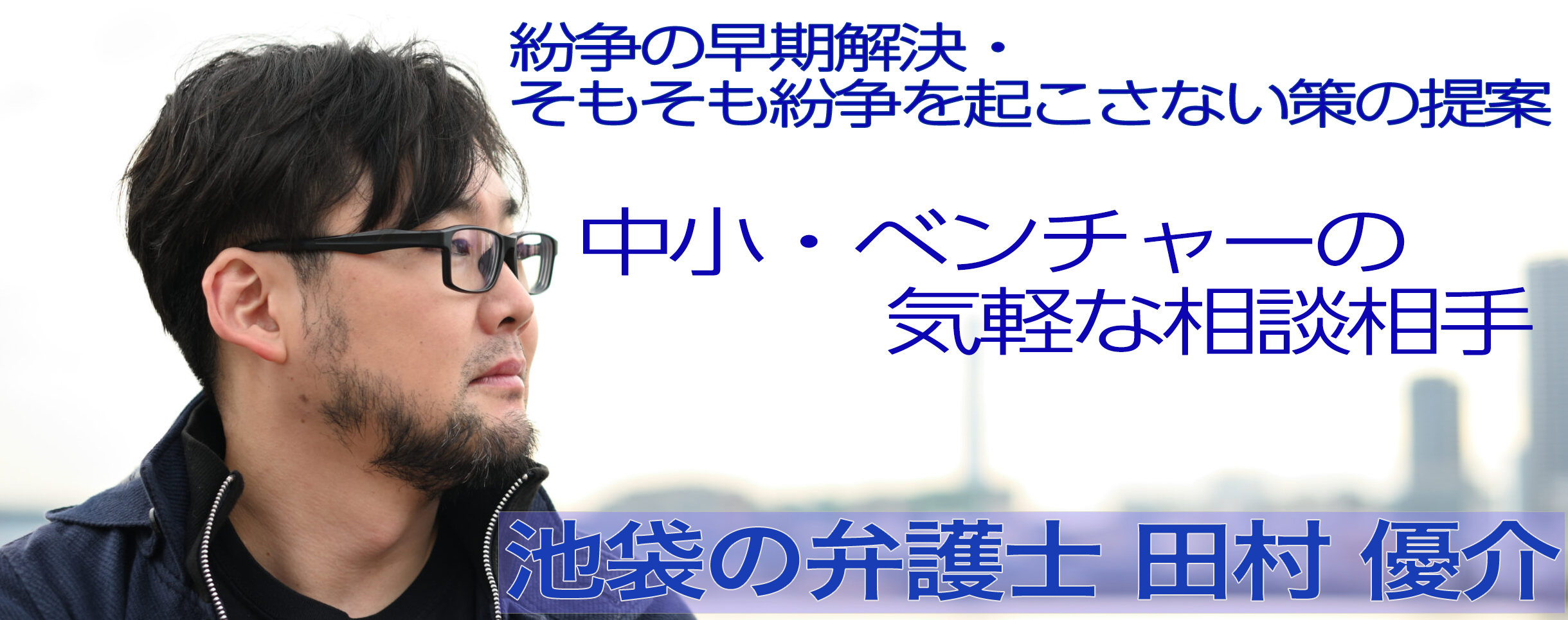




コメント