池袋の弁護士・田村優介です!
2025年6月の労働施策推進法の改正、「何から手をつければ…」とお悩みではありませんか?
この記事を読めば、カスハラ対策や治療と仕事の両立支援など、法改正の重要ポイントと、企業が今すぐやるべき具体的な対応策がわかります。法改正への対応は、単なる義務ではなく、優秀な人材の定着に繋がる重要な経営課題です。専門家がチェックリストも交えて徹底的にわかりやすく解説します!
1. 2025年労働施策推進法等改正の背景と目的
「最近、従業員の離職が多くて困っている…」「ハラスメントやメンタルヘルスの問題に、どう対応すればいいかわからない…」
こんなご相談は、企業の経営者や人事担当者の方からよく寄せられます。解決策はないのか、どうしたらもっと良い会社になるのか、知りたいですよね。
実は、その重要なヒントが、2025年6月4日に成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に隠されています。この法改正がなぜ今行われたのか、その背景と目的を、弁護士が徹底的にわかりやすく教えます!ぜひ、お読みください。
1.1 労働力人口の減少と人材定着の重要性
今回の法改正における最も大きな背景は、日本が直面している深刻な「労働力人口の減少」です。少子高齢化の影響で、働く世代(生産年齢人口)が年々減り続けているという事実は、すべての企業にとって無視できない課題となっています。
以下の表は、日本の生産年齢人口(15歳~64歳)の推移と将来の推計です。
| 年 | 生産年齢人口 | 総人口に占める割合 |
|---|---|---|
| 2020年 | 7,509万人 | 59.5% |
| 2030年(推計) | 6,875万人 | 57.6% |
| 2050年(推計) | 5,275万人 | 51.8% |
(出典:総務省統計局「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)」より作成)
このように、働き手の確保がますます難しくなる時代において、企業が持続的に成長していくためには、新たな人材の採用競争に勝つこと以上に、今いる従業員一人ひとりに長く安心して働いてもらい、定着してもらうこと(人材定着)が極めて重要になります。もはや人材は「採る」時代から「育て、定着させる」時代へと、経営戦略の転換が求められているのです。
1.2 多様な働き方を支える職場環境整備の必要性
労働力が限られる中で企業が成長を続けるには、これまで以上に多様な人材の活躍が不可欠です。育児や介護をしながら働く人、病気の治療と仕事を両立させたい人、経験豊富なシニア世代など、様々な背景や事情を持つ人たちがいます。
こうした多様な人材がそれぞれの能力を最大限に発揮するためには、安心して働ける職場環境の整備が絶対条件となります。具体的には、以下のような環境が求められます。
- パワーハラスメントやセクシャルハラスメントがないこと
- 顧客や取引先からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)から従業員が守られること
- 病気になっても、治療を受けながら働き続けられる支援制度が整っていること
- 性別に関わらず、誰もがキャリアアップを目指せる公平な機会があること
誰もが「この会社で働き続けたい」と思える魅力的な職場環境を整えることこそが、優秀な人材を惹きつけ、企業の競争力を高める最大の鍵となります。今回の法改正は、こうした社会全体の要請に応え、企業による職場環境整備の取り組みを国が力強く後押しすることを目的としているのです。
2. 【ポイント別】改正労働施策推進法等の主な変更点
2025年6月から順次施行される法改正、いったい何がどう変わるのか、気になりますよね。特に企業の人事労務担当者の方が押さえておくべき重要なポイントは3つあります。今回の法改正は、労働施策総合推進法だけでなく、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法など、複数の法律にまたがる大きな変更なんです。でも、ご安心ください!弁護士が、それぞれのポイントを中学生でもわかるくらい、徹底的にわかりやすく解説します!
2.1 ハラスメント対策の強化:カスハラ対策の努力義務化
これまでも、職場におけるパワーハラスメント(パワハラ)対策は、企業の規模を問わず義務化されていました。今回の改正で新たに注目されているのが、顧客や取引先からの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対策が、企業の努力義務として法律に明記されたことです。従業員を守るための体制づくりが、これまで以上に重要になります。
2.1.1 企業に求められる具体的な措置
「努力義務って、具体的に何をすればいいの?」そんな疑問が聞こえてきそうですね。厚生労働省の指針などを参考にすると、企業には以下のような対応が求められます。これらを参考に、自社に合った対策を検討しましょう。
- 従業員からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備(相談窓口の設置など)
- 被害を受けた従業員への配慮のための取組(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者への対応など)
- カスハラを予防するための取組(対応マニュアルの作成や研修の実施、社内への啓発活動など)
- 国や地方公共団体が実施する広報活動、啓発活動などへの協力
これらはあくまで「努力義務」ですが、従業員が安心して働ける環境を作ることは、人材の定着や企業の評判にも直結する大切な取り組みです。
2.1.2 相談窓口の設置と運用の注意点
カスハラ対策の第一歩は、従業員がいつでも安心して相談できる窓口を整備することです。既に設置されているパワハラなどの相談窓口を、カスハラの相談窓口として兼用することも可能です。その際は、カスハラも対象であることを従業員にしっかり周知することが大切ですよ。
窓口を運用する上での注意点は次の通りです。
- プライバシーの保護:相談者のプライバシーが厳守されることを明確に示し、安心して話せる環境を整えましょう。
- 不利益取扱いの禁止:相談したことを理由に、解雇や降格などの不利益な取扱いをしてはならないことをルール化し、周知徹底してください。
- 担当者への研修:相談担当者には、カスハラに関する正しい知識や、傾聴スキル、適切な対応手順などを学ぶ研修を実施することが不可欠です。
2.2 治療と仕事の両立支援制度の拡充
従業員が、がんやメンタルヘルス不調などの病気の治療をしながら、安心して働き続けられるように支援することも、今回の法改正で強化されたポイントです。これまでも指針などで示されていましたが、労働者の申し出に応じて、治療と仕事の両立支援のための措置を講じることが企業の努力義務となりました。
2.2.1 対象となる傷病の範囲
「どんな病気が対象になるの?」という質問もよく受けます。法律では特定の病名が列挙されているわけではなく、「傷病の治療を受けながら就労する労働者」と広く定められています。具体的には、以下のような傷病が想定されます。
- がん
- 脳卒中、心疾患などの脳・心臓疾患
- 糖尿病、肝炎などの生活習慣病
- うつ病などのメンタルヘルス不調
- その他、継続的な治療が必要な難病など
従業員から申し出があった場合には、病名を問わず、まずは真摯に耳を傾ける姿勢が大切です。
2.2.2 両立支援プランの策定と運用
両立支援を円滑に進めるためには、「両立支援プラン」の策定が有効です。これは、労働者本人、会社、そして主治医などが連携して作成する個別の支援計画のこと。具体的には、以下のような内容を盛り込みます。
- 治療のスケジュール(通院日、入院期間など)
- 就業上の配慮(時短勤務、在宅勤務、業務内容の変更など)
- 休暇制度の利用(年次有給休暇、病気休暇など)
- 情報共有の方法や連絡体制
大切なのは、一度プランを作って終わりではなく、労働者の体調や治療の状況に合わせて、定期的に見直しを行うことです。柔軟な対応が、従業員の安心感につながります。
2.3 女性活躍推進に関する情報公表義務の拡大
女性が個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、企業には女性の活躍に関する情報の公表が義務付けられています。今回の改正で、特に「男女の賃金の差異」の公表義務がある企業の範囲が大きく拡大されました。多くの中小企業が新たに対象となるため、他人事ではありませんよ!
2.3.1 男女の賃金差異の公表義務対象企業の変更点
具体的に、対象となる企業がどのように変わったのか、下の表で確認してみましょう。これまで対象外だった企業も、2025年6月以降は対応が必要になる可能性があります。
| 項目 | 改正前(~2025年5月) | 改正後(2025年6月~) |
|---|---|---|
| 対象企業 | 常時雇用する労働者数が301人以上の企業 | 常時雇用する労働者数が101人以上の企業 |
この変更により、これまで準備を進めてこなかった101人以上300人以下の企業は、早急な対応が求められます。自社の労働者数を今一度確認してみてくださいね。
2.3.2 公表すべき情報と方法
公表が義務付けられているのは、「男女の賃金の差異」です。これは、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合で示したもので、以下の3つの区分でそれぞれ算出して公表する必要があります。
- 全労働者
- 正規雇用労働者
- 非正規雇用労働者(パート・有期雇用労働者)
公表は、事業年度終了後、おおむね3か月以内に行う必要があります。公表方法は、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や、自社のウェブサイトなどが一般的です。求職者や社会からの信頼を得るためにも、誠実な情報開示を心がけましょう。
3. 法改正に向けて企業が今すぐ準備すべきこと【対応チェックリスト】
「法改正は分かったけれど、具体的に何から手をつければいいの?」そんなお悩みを抱えていませんか。ご安心ください!法改正の施行に向けて、企業が今すぐ取り組むべきことをチェックリスト形式で分かりやすくまとめました。一つひとつ確認しながら、着実に準備を進めていきましょう。
3.1 就業規則の見直しと改定
今回の法改正で新たに追加された義務や努力義務に対応するため、就業規則の見直しは必須です。特に、カスタマーハラスメント(カスハラ)に関する方針の明確化や、治療と仕事の両立支援に関する制度を盛り込む必要があります。どこをどう変えればいいのか、下の表で確認してみましょう。
| 関連する改正内容 | 見直すべき規定(例) | 規定内容のポイント |
|---|---|---|
| ハラスメント対策の強化(カスハラ) | 服務規律、懲戒規定 | 従業員が顧客等からの著しい迷惑行為(カスハラ)を行った場合の禁止事項や懲戒事由を明記。また、従業員をカスハラから守るための会社の方針を記載。 |
| 治療と仕事の両立支援 | 休職・復職規定、休暇制度 | がん、脳卒中などの治療を受ける従業員が利用できる両立支援制度(短時間勤務、時差出勤、テレワークなど)を明記。申出の手続きや適用条件を具体的に定める。 |
就業規則の変更は、従業員代表の意見を聴取し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。専門家である社会保険労務士に相談しながら進めると、スムーズで安心ですよ。
3.2 社内相談体制の整備・周知
カスハラや、病気の治療と仕事の両立に関する悩みは、従業員が一人で抱え込みがちです。安心して相談できる窓口があることは、従業員の定着と早期離職の防止に直結します。これは絶対に整備しておきたいポイントです。
すでに設置されているハラスメント相談窓口が、これらの新しい相談内容にも対応できるか確認しましょう。もし対応が難しい場合は、新たに専門の窓口を設置することも検討すべきです。相談体制を整える際は、以下の点に注意してください。
- 相談担当者を複数名配置し、男女両方から選べるようにする。
- プライバシー保護を徹底し、相談内容が外部に漏れない体制を構築する。
- 相談したことを理由に、解雇や降格などの不利益な取扱いをしないことを明確に規定し、周知する。
- 相談窓口の存在を、ポスターの掲示や社内イントラネット、研修などを通じて全従業員に繰り返し周知する。
3.3 管理職・従業員への研修実施
新しいルールや制度を作っても、それが社内に浸透しなければ意味がありませんよね。法改正の内容を正しく理解し、全社的な意識を高めるために、研修の実施は非常に効果的です。
特に、部下を持つ管理職には、カスハラ発生時の初期対応や、部下から治療と仕事の両立について相談された際の適切な対応方法など、より実践的な研修が求められます。全従業員に対しても、法改正の概要や相談窓口の利用方法などを周知し、誰もが安心して働ける職場環境を全員で作り上げていくという意識を醸成することが大切です。
3.4 関連する助成金の確認と申請準備
「体制整備や研修にはコストがかかる…」と心配される経営者の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国は企業のこうした取り組みを支援するための助成金制度を用意しています。これを使わない手はありません!
例えば、治療と仕事の両立支援に取り組む企業を支援する「両立支援等助成金」など、今回の法改正に関連する助成金がいくつかあります。助成金は、申請期限や要件が細かく定められているため、早めに情報を確認し、準備を始めることが重要です。まずは、厚生労働省のウェブサイトで、自社が活用できる助成金がないかチェックしてみましょう。
4. 法改正への対応を怠った場合のリスク
「法律が変わったのは知っているけど、具体的に何をすればいいかわからない」「うちみたいな中小企業には関係ないのでは?」そんな風に考えて、対応を後回しにしていませんか?
法改正への対応を怠ると、実は思わぬところで大きなリスクを抱えることになりかねません。放置することで企業が被る可能性のある、深刻なデメリット。ここでは、弁護士がそのリスクを中学生でもわかるくらい徹底的にわかりやすく教えます!
4.1 行政指導や企業名公表の可能性
今回の法改正で定められた義務、例えば女性活躍推進法に基づく情報公表などを適切に行わない場合、行政から是正を求める指導が入る可能性があります。それでも改善が見られない悪質なケースでは、最終的に企業名が公表されることもあり得ます。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 助言・指導 | 管轄の労働局から、法に定められた措置を適切に実施するよう助言や指導が行われます。 |
| 勧告 | 指導に従わない場合、より拘束力のある行政指導として勧告が出されます。 |
| 企業名の公表 | 勧告にも従わない場合、厚生労働省のウェブサイトなどで企業名が公表されます。一度公表されると、企業の社会的信用は大きく損なわれてしまいますよね。 |
また、カスハラ対策のような「努力義務」だからといって軽視は禁物です。具体的な対策を講じていないと、次に説明するような訴訟リスクに直接繋がってしまうのです。
4.2 従業員からの損害賠償請求(訴訟リスク)
企業には、従業員が安全で健康に働けるように配慮する「安全配慮義務」(労働契約法第5条)が課せられています。今回の法改正で求められているハラスメント対策や、治療と仕事の両立支援を怠った結果、従業員が精神疾患を発症したり、退職せざるを得なくなったりした場合、どうなるでしょうか?
その答えは、企業が安全配慮義務違反を問われ、従業員から高額な損害賠償を請求される可能性がある、ということです。裁判になれば、多額の賠償金だけでなく、企業の評判失墜や対応に要する多大な時間と労力など、経営に深刻なダメージを与えます。
4.3 企業イメージの低下による経営への悪影響
法改正への対応を怠っていることが世間に知られた場合、企業のイメージは大きく傷つきます。いわゆる「ブラック企業」というレッテルを貼られてしまうかもしれません。
- 採用難と人材流出:「従業員を大切にしない会社」という評判が広まると、新しい人材の採用は非常に困難になります。それだけでなく、今いる優秀な従業員も愛想を尽かして辞めてしまうかもしれません。人材不足は、企業の成長を妨げる最大の要因の一つです。
- 顧客・取引先からの信頼喪失:コンプライアンス意識の低い企業と見なされ、顧客や取引先が離れていく可能性があります。特にBtoB取引では、相手企業のコンプライアンス体制を重視する傾向が年々強まっています。
法改正への対応は、単なる義務の履行ではありません。従業員を守り、企業の持続的な成長を実現するための、極めて重要な「未来への投資」なのです。リスクを正しく理解し、今すぐ準備を始めましょう。
5. まとめ
2025年6月の労働施策推進法改正、対応すべきポイントはご理解いただけましたか?カスハラ対策や治療と仕事の両立支援など、やるべきことが多くて大変だと感じますよね。でも、この法改正への対応は、単なる義務ではありません。従業員が安心して働ける職場を作ることは、優秀な人材の確保や企業のイメージアップに直結する絶好のチャンスです。何から手をつければ良いか迷ったら、お気軽にご相談ください。
早めの準備で、変化をチャンスに変えましょう!
池袋の弁護士・田村優介へのお問合せはこちらから!
ご相談の予約、お問い合わせは、下記からお気軽にどうぞ。
ブログの更新情報はTwitter(X)でお知らせしています!フォローお願いします
池袋の弁護士・田村優介(第二東京弁護士会・城北法律事務所)
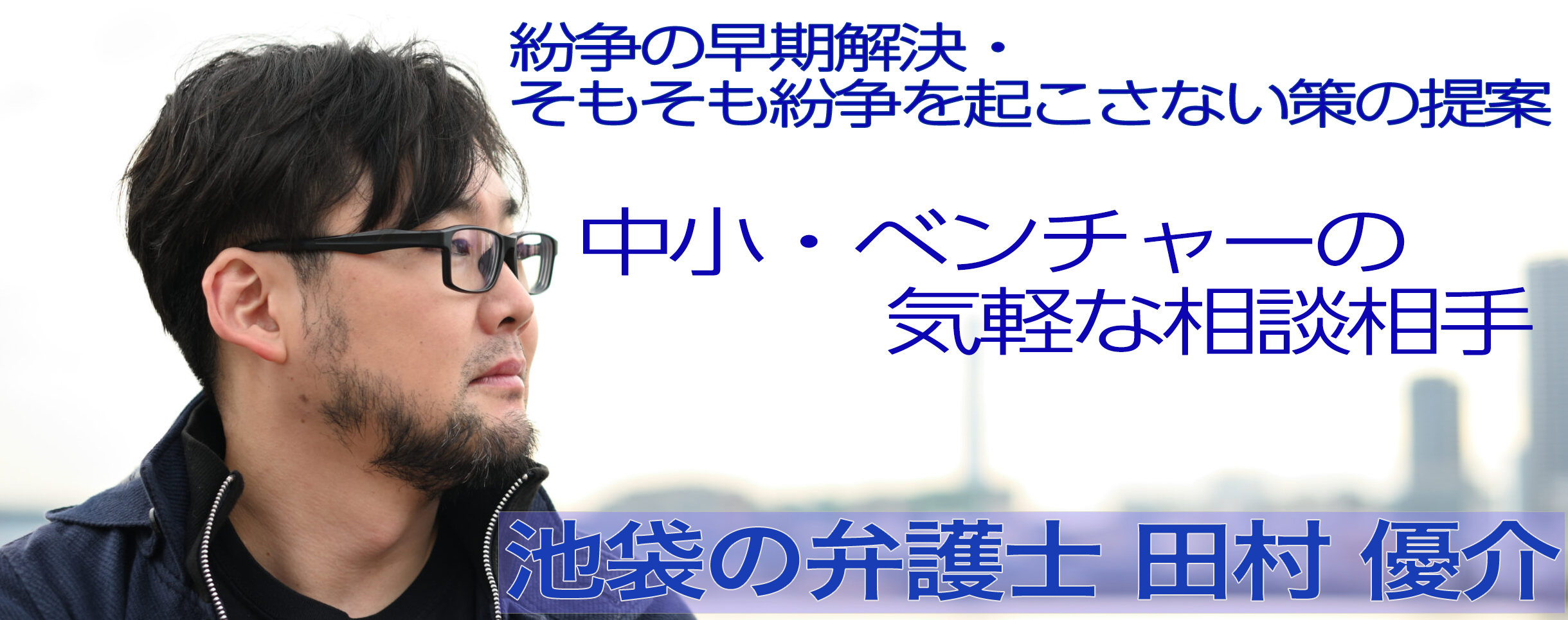




コメント